こんにちは。メグミです。
英語のテスト問題において、
子供たちの苦手分野はさまざまです。
文法・英単語・長文読解・英会話文・・・などなど・・・
なかでも「リスニング問題」が聞き取れなくて、答えられなくて苦手~!
という子も多くいます。
なのに、中学校の今の現状では
「リスニングの授業」というのが皆無に等しく、
それなのにテストでは、一番先頭に、しかも配点多く出てくるのです!!
私は中学校のカリキュラムの中で、「リスニング問題」が一番無責任だなーと思います。
最近ではALTの先生がさかんに授業に登場して
「会話や聞き取り」の環境を増やしていますが、
正直、
「英会話の聞き取り」と「テストのリスニング問題」は別次元です。
もちろん、
基本は英会話・英文が聞き取れているか?を問うのですが、
やはり「テスト」というものには「テクニック」が必要です。
今日はそのテクニック的な部分で一番に手を付けてほしい箇所をお伝えします。
<優先すべきリスニングテスト克服勉強法>
まず、「テスト形式」に慣れることが先決です。
「リスニングテスト」と一言でいっても、いろんなパターンがあります。
そのパターンに「慣れる」ことがまず大事です。
1例をあげると、こんな感じです。
(例)長いスピーチ文の後、設問5問を口頭で出され、解答文を4択程の中から選択する形式
(パターン1.)スピーチ文→設問5問→スピーチ文→設問5問
(パターン2.)スピーチ文×2回→設問5問×2回
というパターンがあったりします。
え?これだけの違い?と思われるかもしれませんが、
これが「解く側」からすると、おそろしく違うのです!!
どちらかというと(パターン1.)の方が、1巡目で「聞き逃した箇所が直後すぐ分かる」ので
2巡目で落ち着いてそこに集中して「聞き直す」ことができます。
ところが(パターン2.)では、スピーチ文を2回「聞いた後でどこが問われた」に気づくので
「聞き直す」という行為ができないのです。
なので(パターン2.)の方が、スピーチ文2回で「端から端まで聞き取っておかなければ」という精神的「プレッシャー」が大きいとも言えます。
テストに臨む事前に、こういった「形式の違い」を生徒自身が理解・想定して、かつ慣れておかないと
本番で問題を解きながら「ああ、そうだったのか!」なんて気づいても、戸惑い・焦りが先走り、
本当は分かっているものも、聞き取れているはずの文も、解けないで終わるのです。
これが原因で、リスニング問題がかなり苦手になっている子が多いです。
問題の形式を理解するのに時間を費やし、焦っているだけなのに
それもひっくるめて全て「聞き取れなかった・・」と本人が結論付けてしまっているのです。
周りも、「本人がそう言うのだから、聞き取れてないのだろう」と決めてしまっています。
まさか、「形式に戸惑って焦り、聞き漏らしているだけ」なんて予想もしないのです。
親御さんにはそこまでは把握できないでしょうから・・・・。
ここは学校の先生が「リスニングテスト用の対策授業」を定期的にでも行うべきです。
私は自分の授業の中では「形式に慣れるように」と説明を入れてリスニングを行っています。
リスニングテストは、「ALTの先生の話を単に聞き取れるようになる」とは話が違うのです。
テスト形式に慣れ、パターンが自分の中でいくつも想定できているだけで
取れる点数は格段に上がります。
もし学校の授業でこういった練習ができないなら
自分一人でもリスニング問題をたくさん経験してください!!!
その際、「聞き取る」こともですが、「テスト形式の把握」も、ひとつひとつ頭に入れていってください。
まずは、ここから克服していきましょう!
今日も最後までありがとうございました。
野原めぐみ
はじめまして。野原めぐみと申します。英会話講師をやっております。長年指導させていただいている経験から、
「中学英文法」を体感的にまで理解できることが、英会話上達の最短距離!
だと実感しています。
非母国語圏の人間だからこそ分かる、「肝」をズバリ提供できればと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
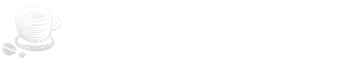






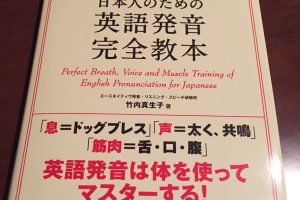

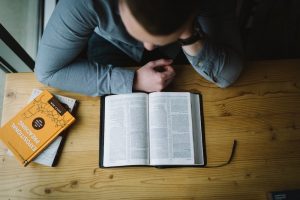












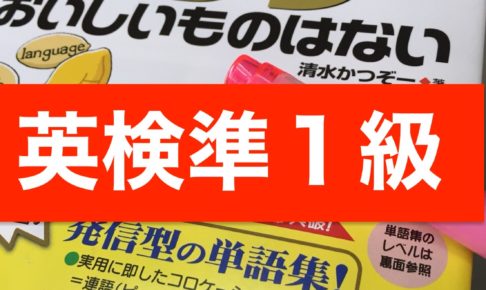


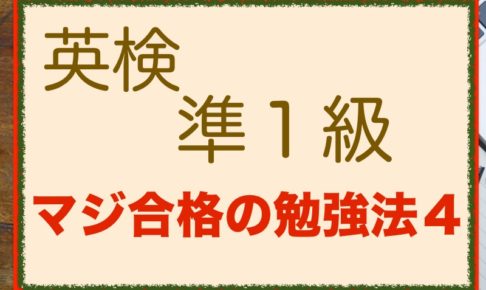
コメントを残す